ホーム > 防災コラム一覧 > 地震対策 > 帰宅困難者対策
帰宅困難者対策
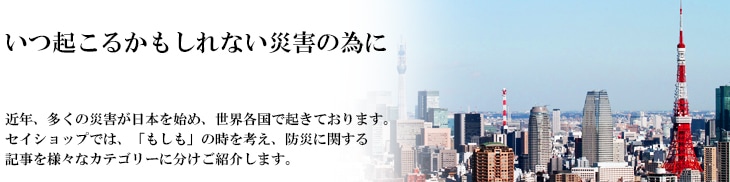
いざという時のために 職場に用意しておきたい防災グッズ【ジャンル:防災用品リスト】

日中であれば、職場にいて災害に遭うという状況も考えられます。
内閣府が行った調査によると、2011年3月11日の東日本大震災では、首都圏で推定約515万人が、当日自宅に帰宅できない帰宅困難者となりました。
都心部で災害に巻き込まれた際の移動手段 【ジャンル:地震対策コラム】

マグニチュード(M)7級の地震で、最悪の場合、死者が23000人、経済被害が約95兆円に上るとの想定が発表されています。
このような大規模の震災に直面した時のためにあらかじめ知っておきたいのが「地震が起きた時の移動手段」に関する知識です。
震災後は基本的に「むやみに動かない」ことが推奨されていますが、必ずしもじっとしておける状況とは限らないのです。
地震直後、道路や鉄道など交通網は寸断します。とくに都市圏では、仕事をしていた人、たまたま買い物に来ていた人、学生などが、急な震災によりターミナル駅を中心にして長期間足止めされます。首都直下地震の想定では、歩いて帰れる距離に住む帰宅困難者予備軍の人たちは、時間の経過と共にしかたなく徒歩で家に帰る人が出ますので徐々に減っていきますが、徒歩で帰ることが困難な448万人の帰宅困難者はターミナル駅周辺に滞留し続けます。
長期間にわたってインフラが破壊される広域災害において、とくに昼と夜の人口が大きく異なる都市圏の帰宅困難者問題は、想像するよりも深刻であることをまず知ることが大切です。日本の災害対策では、私たちの命はそれぞれの市区町村という行政の単位が守ることになっています。そのため各行政は、税金などから予算をとって、住民のために、食料を備蓄したり、毛布を取りそろえるなどの何がしかの対策をしています。しかし、他県から通勤・通学している人たちは、地域の住民ではないので、この人達の分の備えは確保されていません。私たちが頼りにするその土地の行政機関にとっては、帰宅困難者たちはある意味で部外者なのです。そのため東京都では、7割がサラリーマンという日本の社会システムにおいて、会社単位で従業員を帰宅困難から守るように定めた「東京都帰宅困難者対策条例」を2012(平成24)年3月に制定し、翌2013(平成25)年4月から施行されています。
この帰宅困難者対策のコラムでは、東京都帰宅困難者対策条例などを中心に、自助(自分の身は自分で守る)ことや帰宅困難を取り巻く状況についての解説など対策について掘り下げていきたいと考えています。

