ホーム > 防災コラム一覧 > 防災用品 > 「買ったは良いけれど……」非常食の賞味期限切れ問題にどう対応する?
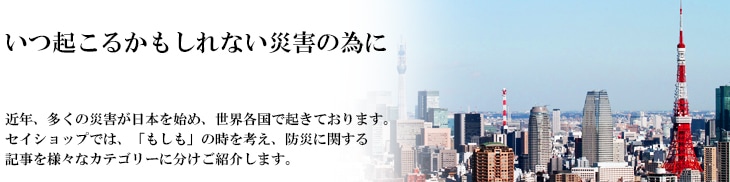
「買ったは良いけれど……」非常食の賞味期限切れ問題にどう対応する?

非常食として長期備蓄食である缶詰や乾パン、保存性の良いレトルト食品などを購入してあるというご家庭や企業も
多いと思います。
ところで、「我が家は非常食を備蓄しているから安心」という方は、ちょっと 賞味期限を確認してみてください。
保存性の良いものでも、食品の賞味期限は「3年」もしくは「5年」のものが多くなっています。
東日本大震災のあった 2011年に購入したものであれば、そろそろ期限切れや、期限が迫っているものがあるかもしれませんよ。
賞味期限切れの非常食は廃棄処分に……

非常食として購入したものの、実際に非常食として使用する機会がないままに賞味期限が迫ったり、期限切れとなってしまうケースは多いものです。
期限が迫っていても期限切れになる前なら、ご家庭なら普段の食事に取り入れたり、企業の場合なら社員に分配したりといったこともできますが、 期限切れになってしまった非常食については廃棄されているのが現状のようです。
企業であれば、産業廃棄物となり廃棄コストもかかってしまいます。
日本の人口に対する食品廃棄率は、消費大国であるアメリカを上回り世界一高いとも言われています。
災害に備えて非常食を備蓄することは大切ですが、幸いにして長期間大きな災害に見舞われることがなく食べる機会がなかった非常食だとしても、 廃棄せずに済む方法を考えておく必要があると言えるでしょう。
食べきれない食品はフードバンクへ

企業などで大量の非常食の入れ替えが必要になる場合には、 「フードバンク」に寄付するという方法があります。
フードバンクというのは、まだ十分食べられるにも関わらず、規格外であるなどさまざまな理由によって 廃棄しなければならない食品を寄付し、 食品の支援を必要とする福祉施設や団体などに再配する活動です。
1960年代にアメリカで始まり、世界各国に広まりました。
日本でも2002年にセカンドハーベスト・ジャパンが設立されて以来、各地にフードバンクの団体が広がっています。
セカンドハーベスト・ジャパンでは、加工食品の場合、 原則として賞味期限が1ヵ月以上のものが引き取りの対象となります。
賞味期限切れの非常食は受け取ってもらえませんが、賞味期限1ヵ月以内だとしても数量や品目によっては受け取ってもらえる場合もありますので、問い合わせてみるのが良いでしょう。
企業だけでなく、個人の寄付も受け付けてくれます。
セカンドハーベスト・ジャパン
https://2hj.org/
防災備蓄品の寄贈を検討中の企業の方
https://2hj.org/support/food/emergency_food_supplies_faq.html
「非常食を日常の食事に取り入れる」という考え方

賞味期限前に寄付するという方法もありますが、せっかく購入した食品を、非常時や賞味期限が近づくまで食べずに備蓄し続けておくのではなく、 定期的に食事に取り入れていくという考え方を取り入れるのも良いでしょう。
日常の食事に取り入れることを考えるのであれば、「長期保存できるかどうか」「保管しやすいかどうか」といった観点だけでなく、 「日常的に食べているものと同じように美味しく食べられるかどうか」といった点も、非常食を購入する際に重要であると言えます。
非常食の廃棄を避けるための考え方の一つとして、 「ローリングストック法」があります。
これは、非常時に備えて食べずに備蓄しておくのではなく、 月に1~2回非常食を食べる日を設けて、食べたら買い足すという
考え方です。
賞味期限切れを防ぐことができるだけでなく、日常的に非常食を食べておくことによって、 いざ本当に災害などの非常事態が
訪れたとしても普段から食べ慣れたものを 食べることができるため安心感を得られやすいという利点があると言われています。
最近では、非常食を美味しく食べるためのアレンジメニューのレシピなどもネットで多数公開されています。
こうしたものも活用して、非常食を定期的に消費しつつ買い足していくと良いでしょう。
家族の人数×1日分(3食)×備蓄する期間(1週間分など)=食数
といったように食数を決めてその食数をまとめて買うのも良いのですが、1ヵ月分の 予算を決めて徐々に買い増していくのも良いでしょう。
そして、製造された時期が古いものから消費していくことで、常に新しいものが備蓄されているという状況を意図的に作り出すことができます。
そうして非常食として備蓄してある食品を、防災の日(9月1日)や、防災とボランティアの日(1月17日)などのタイミングで
食べてみるのも良いですね。
上記で紹介したような方法を取り入れつつ、ご自身やご家族のライフスタイルに適した食料備蓄の方法を見つけ出していただければと思います。


